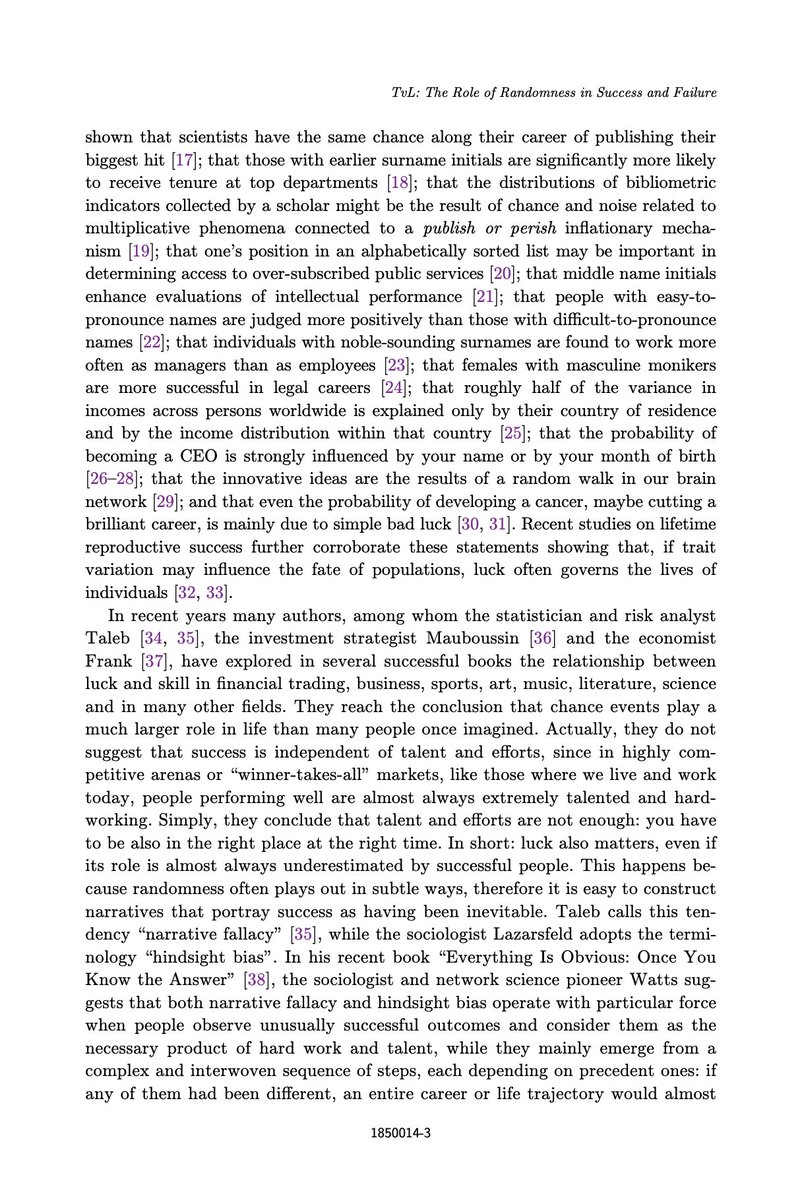成功するのは才能ある人ではなくただ運のいい人である(2022年イグノーベル経済学賞)
>@ka2aki86: 2022年のイグノーベル経済学賞の「成功するのは才能ある人ではなくただ運のいい人であることの数学的説明」が超おもしろい。この通りならば自分に才能があるかを悩む必要はないし、成功した人(≒運のいい人)に嫉妬したり過剰に持ち上げたりする必要もないことになる。少し気が楽になる研究。
>@ka2aki86: 運ゲーにおける生存戦略としては、
>①変化が激しく新参者にもチャンスがありそうな環境を選び、
>②長く続けられる活動を見つけて、
>③確率だと割り切って試行回数を増やす。
>に落ち着きそう。成功するかは誰も保証されてないなら、楽しめてやり続けられる活動を見つけるほうが近道。
公正世界仮説を否定する研究
継続して
試行回数を増やすことが大事
> 成功にはわけがある、とは限らない
> 受賞者:アレッサンドロ・プルチーノ、アレッシオ・エマヌエーレ・ビオンド、アンドレア・ラピサルダ(イタリア)
> 受賞理由:どうして成功するのは最も優れた人ではなく最もラッキーな人なのか、を数学的に説明
>@fladdict: 基本的にはサイコロゲームでの平均回帰のはずなんだけど… 最初に6が出た人は、目立って注目ボーナスが出て、次のサイコロが1D+3になり… という感じで、累進的にボーナスがつく環境もある。そういう環境だと、初動がよいほど拡大再生産できるので、「初動で目立つ」ことが、すごい重要になっちゃう感
初動が大事、マタイ効果が働くから
>@inaba_desu: 2022年のイグノーベル経済学賞を受賞した
>「なぜ最も才能のある人ではなく、最も幸運な人が成功することが多いのかを数学的に説明したことについて」
>という研究が話題になっていて面白かったので、土日を使って気合いで読みました。
>日本語訳で要約してみます。
>1/n
>@inaba_desu: 結論、
>・最も成功した人は最も才能に恵まれた人ではない
>・一方で、人生で幸運な出来事に(高頻度で)見舞われた人は最終的に大きな富を築いた
>・同時に、不運な出来事に(高頻度で)遭遇した人は最終的な資産ランキングにおいて底辺に留まった。
>2/n
科学者は偶然有益な発見をしがち
物理学者のキャリアの長さと、引用数が多い論文を出す時期に関係が無かった
キャリアの最初に凄い論文を発表する人もいれば、晩年に発表を出す人などばらつきがあった
結論などは、上に挙げたまとめの内容と同じ
>・最も成功した人は最も才能に恵まれた人ではない
>・一方で、人生で幸運な出来事に(高頻度で)見舞われた人は最終的に大きな富を築いた
>・同時に、不運な出来事に(高頻度で)遭遇した人は最終的な資産ランキングにおいて底辺に留まった。
やはり、リスク・リターン管理しながら試行回数を増やすのが運ゲーにおいて大事
リスク・リターン管理 -> 不幸の発生リスクよりも幸運のリターンの方が期待できる行動