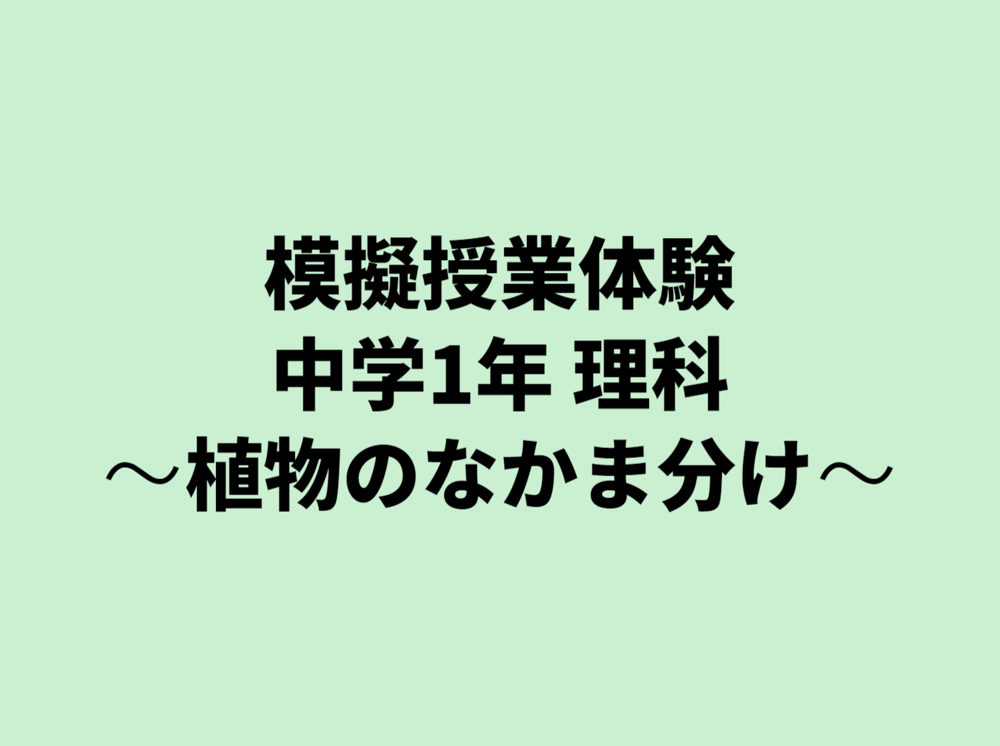中学校 理科 1年 【植物の仲間分け】
新渡戸文化小中学校・高等学校 奥津憲人
シンキングツール使用のポイント
<1時間目>
1時間目は「分類・整理」をするためにツールを活用
自分なりの「分類・整理」方法を見出すことが目的
<2時間目>
2時間目は「発散→収束」のイメージをもつための、「ブレスト→絞る」という流れで活用
使用するものを選ぶときの基準や優先順位をつけるようになることが目的
題材についてポイント
単元は植物の仲間分け→「植物の分類はどこを見るといいか」を自分なりに見出す
身近な野菜を使うことで、日常との関連を意識する
<1時間目>
<2時間目>
授業全体の流れ
<1時間目>目の前の植物がコケ植物・シダ植物・被子植物・裸子植物のいずれに分類されるかを知る
導入:身近な植物に触れる
植物の分類を確認後、冷蔵庫にある野菜を持参する
展開1:野菜を分類する
持参した植物がどの分類に当てはまるかを、キャンディーチャートを使って分類する
展開2:植物の分類チャートをつくる
持参した野菜や、友人の持っている野菜を使って、オリジナルの分類チャートをつくる
展開3:野菜を分類する
作成した分類チャートを使って、いくつかの植物を分類する。カードをトーナメントのように動かすことで、それぞれのグループに割り当てられるようにしていく(カードムービング)
まとめ:植物の分類方法を知る
自分なりに、植物を分類するときにはどこを見るべきか、ポイントを定める
1時間目のポイント
<2時間目>自分の好きな野菜のアピールポスターをつくる
展開1:野菜を挙げる
Yチャートを用い、様々な植物をブレスト的に上げる(発散)
展開2:野菜を分類する
今回題材にする植物を決めるために、2軸で分類する。”好き”かつ○○というものを題材にする(収束)
展開3:野菜について調べる
クラゲチャートを使い、野菜について調べる。栄養価、価格、保存については必須、それ以外のポイントも自分で調べる(発散)
展開4:野菜をアピールするポスターをつくる
ポスターにする際、どの情報を入れるかを考えるため、Yチャートを使う(収束:動的シンキングツール?)
展開5:みんなのポスターを相互評価する
提出箱で集約し、共有して一人3つのポスターを選び、評価する。評価は文章で行い、良かった点と改善点を書くようにする。