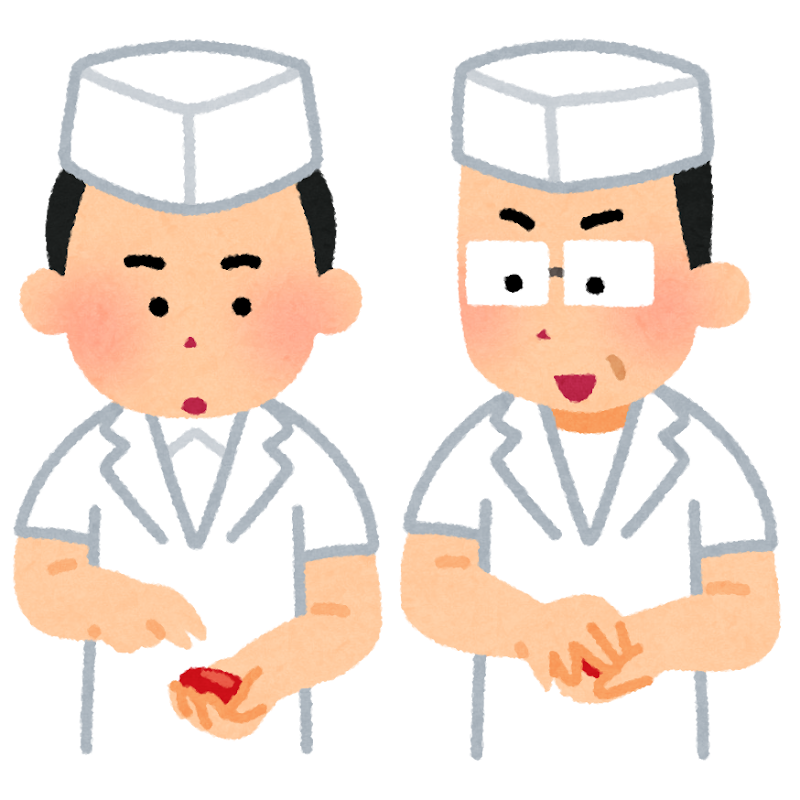守破離
「守破離」とは武道とか書道とか、なんちゃら道でよく使われる教育法のことです。
Wikipediaから落語の例
守:古典落語を忠実に表現することができる。
破:古典落語をより面白くアレンジすることができる、あるいはよりわかりやすく表現することができる。
離:経験を活かし新作落語を作ることができる。あるいは、落語から進化した新たな芸風を作ることができる。
師範に当る人はまず自分の身に着けていることを人に伝えるために、手法化します。
弟子たちは
・それを守る
・破る(改良する)
・離れていく(創造する)
ことによって本来師範が身に着けていた思想を含めて獲得していくという古来から教育法です。
でもこれ武道などだけじゃなく、一般の教育や、ビジネス系のフレームワーク(SWOT分析とかデザイン思考とか)でも同じような手法化がよく行われています。
一旦手法化してしまう問題点は、情報が圧縮されてしまうので、もともとの目的や考え方などが失われてテクニックになってしまうこと。そしてそのテクニックを使うことが目的化して、守の段階から抜け出せず停滞してしまう人が大量に発生してしまことです。(SWOT分析もしらないんですか?とか、人をマウンティングする道具になってしまったり、効果ないからキャリアポルノとよばれてしまったり)
そういえばアクティブ・ラーニングも手法じゃないとかいろいろ言われてましたね。
デザイン思考は手法じゃなくマインドセットだとか。
でも手法化して情報を圧縮しないと、人には伝えられないのです。
では、そもそも「身に付いた」とはどんな状態のことを言うのでしょうか?
落語の例から見ても、型(守)から始まり、自分なりに状況に応じて応用できる状態、すなわち自分流が使えるようになったときにはじめて身に付いたと言えると思います。
最終的に自分流を作ることを強く意識して、いろいろな手法はそのためのヒントだということを忘れなかったら、「守」の罠にハマらずに学び進めていけるかもしれません。
そういう意味では、まずは好き勝手やってみて自分流(我流)を作ってから基礎を学ぶとうまく成長の好循環に繋がる気もします。
我守破離?